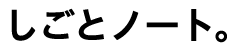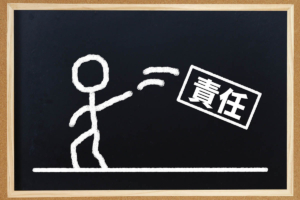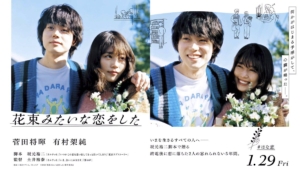以前、クックパッドとD&DEPARTMENTさんが本社を移転するという記事を書きました。

あれは、今年の2月のことでした。そして、ただいま7月半ば。あれからどうなったかなー?ということで続報をお送りします!決して忘れていたわけではありません。
クックパッド、横浜に移転
リリース通り、5月に横浜のWeworkに移転したもよう。
PR TIMESの記事はこちら。

Wework、SOLSOが内装デザイン
写真を見ると、グリーンがたくさんありますね。
植栽計画、植栽運用は『SOLSO』さんだそうです。
都内や、関西でも都心部のおしゃれなショップや施設のグリーンと言ったら『SOLSO』って感じですが、SOLSOのウェブサイトで見るアバンギャルドな雰囲気すら感じるグリーン使いと比較するとちょっとおとなしめな感じもしました。まあショップではなくオフィスですからね。当然と言えば当然かもしれません。が、個人的にはマイオフィスをちょっとアバンギャルドな感じにしたいです。(勝手にやれって感じですよね)

↑こちらはSOLSOさんの写真ではありませんが、こんなグリーンに埋もれたオフィスにしてみたい。
リモートを経て、オフィスでの働き方に戻っていく

ちなみに今でも続いているコロナ禍ですが、クックパッド社の横浜の新オフィスへの移転には『オフィスを中心とした働き方を再始動』という意味があるそうです。
すっかりリモートワークが基本になった企業も多い中、徐々にオフィスへ出勤するスタイルに戻りつつある会社も増えている、という話も聞いていました。
クックパッド社も、一時はリモート化が進んだものの、今では随分とオフィスへ出社するスタイルに戻っているそう。
リモートの一番の問題が、インプット量が少なくなるというもの。
雑談やちょっとした相談、また、働く仲間たちとの距離感や空気感、一体感という合理化できないプラスの効果ってやっぱりあるんですよね。
周りの空気によって高められるモチベーションや、入社まもない社員の場合は「この会社に入社したんだ!」という実感も得られるし、人間関係を築く上でもやっぱり『会って集まって仕事をする』って大事なんだなと感じさせられる、クックパッド社の決断です。
社員同士の雑談から、より良いUI・UXを生む
クックパッドは特に『to C』ビジネスで、ユーザーの些細な使い勝手だとか、コロナ禍の家庭の日常の変化なども、個人の経験値だけでは拾いきれない要素が多いため、なおのこと雑談から得るものの大きさを感じます。
例えば、独身20代の男性エンジニアが、30代子育て中の女性の感覚だったり、休日キッチンで子どものために腕を振るう40代パパの気分なんかはなかなか掴みづらい。
自分が体験していないことは、どんなに情報を集めて想像しても、どうしてもズレが生じてきます。
これはなにもクックパッドだけでなく、どんな企業のどんな職種にでも言えること。
例えば水道工事など、プロフェッショナルの専門技術を提供する場合は必要ないかもしれませんが、サービスや商品の提供の場合はどうしてもユーザーの使い勝手、いわゆるUIとかUXという部分が大事になってきます。
デジタルサービスやスマホだけでなく、身の回りにある、使用する誰かのためにつくられているもの全般にかかわってくる考え方ですね。ユーザーの使い勝手、いわゆるUI・UXをアップデートするには、やっぱり有意義な雑談が効果的。
新オフィスは、期待していたより無機質な印象…

クックパッドの広報記事
『つくり手・生産者を感じることで、 プロダクト開発を加速させるオフィスデザイン』
こちらの記事の最後にフロアの動画があるのですが…意外と無機質…だなあというのが第一印象でした。
前のオフィスは、オープンキッチンや大きな冷蔵庫が空間の核としてあって、他にもワークエリアにもいろいろと遊びの要素があったりして楽しげな雰囲気だったのですが。
移転して間もない、まだ什器が全部入ったというくらいなのでしょうけど、人が入ればもっと雰囲気が変わるかな?と言う気もしますが、、それにしても、超・事務所感。
いい椅子だけど…ていうか、椅子の数多いなーーー!それだけスタッフを抱えていると言うことでしょうけど、いやすごいな、椅子。ワークデスクエリアと打ち合わせエリア、どんだけ椅子あるんだ???っていう、そこに目を奪われました。(そこ?)
元々、Weworkに入居するということで、それほど大きなフロア構造の改装もできないだろうし、どんな感じにするんだろう?と楽しみにしていましたが、手を加えられないせいなのか狙いなのか、ずいぶんとあっさりした印象。
リリースを見ても前の様なキッチンはなさそうだし、いや、他の場所にあるのか、全貌はわかりませんが、ものすごく個人的な感想ですが「思ってたんと違う…」って感じでした。
壁や柱が白いままだし、ここに木の板とか貼ったらもうちょっと柔らかくならない?壁の一面だけカラーにするとか、そういうエリアあっても良くない?食欲が増す様な黄色や赤のさ、、とか勝手に思いましたが。余計なお世話ですけどね。
クックパッドはさらに拡大中
プレスリリースの頭から
当社は、2017年からの10年間をさらなる大きな成長のための事業基盤創りに注力する「投資フェーズ」と定め、積極的な投資を行っています。特に、当社のミッションである「毎日の料理を楽しみにする」を実現するためには、「つくり手を増やすこと」が重要だと考えており、つくり手に向けたプラットフォームサービスの拡大を国内事業の重要施策として位置付けています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000027849.html
とのことですので、投資フェーズ…。さらに拡大していくのですね。すごいねクックパッド。
プラットフォームの拡大ということなので、編集的な要素よりもエンジニアがさらに増えるのかな。それでこの無機質な、もとい、無駄のない内装なのでしょうか。
オフィス空間って、その会社の風土や性格が反映されますよね。おそらく、次なるプランに向けた目的にあったオフィスなのだと思います。
D&DEPARTMENT、引き続き場所を探してます
さて、もうひとつ本社を移転すると言っていたD&DEPARTMENT。
こちらは、夏までには引っ越したい、全国から募集!と言っていましたが、その後どうなったのでしょうか。
もう夏です…。

https://www.d-department.com/category/TEXT_NEWS/DD_TEXT_REPORT_28684.html
まだ決まってないんだそうです。笑
こちらの記事が5月のリリースなので、その後、水面下では進んでいるのかもしれませんが、ナガオカケンメイさんのブログやtwitterを覗いても、特に決定のお知らせがないような…。
いろんなところからお声がけがあって、いろんなところに行ったのだけど、なかなか現実的には難しいのだそう。一般人から見たら、知見も資金力もありそうなD&DEPARTMENTをもってしても、困難だらけなのだそうです。応援したくなりますね。
とはいえ奥沢は夏から耐震工事が始まり、通常の営業はできない状況が迫ってきます。いよいよピンチ!!一時的な避難場所として、仮設店舗としてすぐに使える場所をお貸しいただける方も探しております!!
https://www.d-department.com/category/TEXT_NEWS/DD_TEXT_REPORT_28684.html
危機感が感じられます。笑
いや、なんていうか好きです。この感じ。
「自分たちが手がける意義」の必要性がある
また、レポートには、
今回、「移転先情報募集」と広く呼びかけたことで、今まで自分たちだけでは想像もしなかったような、町づくりごと取り組む案件にお声かけいただくようになりました。その場所に私たちが移る意味を見出せるものについては、その可能性を深堀りしていきたいと思っています。
https://www.d-department.com/category/TEXT_NEWS/DD_TEXT_REPORT_28684.html
という文面もありました。
元々D&DEPARTMENTは、日本各地のよいものを、その土地に一時的にでも暮らし、探し、地元の人や作り手と話すという丁寧なやりかたで紹介していました。
もちろんそういう背景もあってのことでしょうけれど、町づくり案件の依頼が増えたというのも必然な気がしますね。
一時、全国的に『地方創生・町おこし的』なプロジェクトは、東京の巨大な広告代理店が受注して、予算をかけて著名な方のデザインやアーティストが関わったりする大々的なものが乱立しました。
今でもそのパターンが多いかもしれません。 地方だとやはり、依頼する側もされる側も、知見も経験もないせいかもしれませんが。ただ結局、その“黒船来航”的なプロジェクトは、一時的に流行っても衰退してしまうという事例が後を絶たない、という印象です。
受け手側が、ビジネス的うまみだけではなく、きちんと「自分たちが手がける意義」みたいなことを感じているならいいなと思うわけですが、そういう姿勢が行間から滲み出るD&DEPARTMENTならば納得、という感想です。
田舎に暮らしていると『MUJI』が天国に見える(笑)

本社移転とは別に、小さな新しいd&d「d news」という店舗を愛知に開業するにあたり、その準備で代表のナガオカケンメイさんは今、月の半分は愛知県で暮らしているそう。
そこで、それまで苦手だった大型商業施設に入ってびっくりした、という記事を書かれていました。
とても印象的だったのでご紹介します。
https://www.d-department.com/category/TEXT_NAGAOKA/DD_TEXT_REPORT_28002.html
愛知の小さな町に暮らしてみて、日頃何かと必要なものを買いにいくのに、その土地にある大型商業施設、「アピタ」に行ったナガオカさん。「アピタ」は弊地域にもあるのでちょっと笑ってしまいました。。
さて、ナガオカさんが何に驚いたかと言うと。
なんでもあるのです。
https://www.d-department.com/category/TEXT_NAGAOKA/DD_TEXT_REPORT_28002.html
なんでもありすぎて、「これでいいじゃん」という気持ちにもなり、こうして「町の質」が作られていくんだなぁと、思いました。
また、仕入れで沖縄のガラクタ屋を巡っていると大部分が「ニトリ」だったり。
その土地に昔からあるもの、よいもの、ではなくて全国的に安価に広がっているもの。
地元に暮らす人たちの日々の生活で便利に使われるものが、古道具屋にもある。
価格やブランドイメージは置いといて、まあ考えてみれば理解できますよね。それだけ流通し、日常に溢れていると言うことですから。古着屋にユニクロがあるみたいなもんです。
でも、まあやっぱりちょっとガッカリする気持ちはわかります。自分が地元の古道具屋で「ニトリ」を見つけたらやっぱりガッカリする気持ちになると思いますし。地元でもガッカリするんだから、遠方まで行ってそれだとさらにガッカリしますよね。
さらに、昔からあるアノニマスでよいデザインのものを、再発掘して価値を伝えることを生業としているナガオカさんたちからしたら、そのガッカリ感たるやハンパないでしょう。
余談ですが、田舎町に暮らすことになると「MUJI」は天国に思えます。笑 デザインがある。
https://www.d-department.com/category/TEXT_NAGAOKA/DD_TEXT_REPORT_28002.html
生活へのこだわりを提言してくれる・・・・・。そこにある「意識」に、田舎暮らしを始めたばかりの僕は、なんとなく救われもするのでした。
そんな中でもナガオカさんを『天国』と言わしめた無印良品。デザインがある。よくわかります。笑
それでも、やはり無印良品も、なんでもあるし、大量に製造し、安価に販売している。
デザインも提案の意識もあるMUJIですら「『これがいい』より『これでいい』」というコンセプトを掲げています。
量販店や100均の見た目が雑多なものよりは洗練されているけれど、「これでいい」を積み重ねていいのだろうか、とふと考えさせられました。
価値を見出していく、伝えていく
地方にドカンと立つ商業施設や家電量販店。
田舎に住む自分でも、さらに田舎へ行ったり伝統工芸がある地域などにいくと、「こんなに素敵なものがあるのに、そんなどこにでもあるものに消されてしまうなんてもったいない」と思うこともあります。
でも、そこに暮らす人にも、当たり前ですが、安価に便利で快適を享受する権利はあるわけです。
田舎だから田舎らしい暮らしを強要される必要はない。だからといって、やっぱり全国どこでも均一化・均質化していくのは、便利かもしれないけど、つまらない。
その土地にしかない素敵なものってあるわけで、そこに誇りを持ちたい。
暮らし周りのことは大概がユニクロやニトリや100均で済んでしまうけど、それだけでは味気ない。ユニクロやニトリもきちんと商品開発されて製造されていることを、無視するわけではないけれど。
でも時に、作り手の過剰なまでの熱量でできたものなんかにも、惹かれますよね。
便利やテクノロジーと、その土地にしかない素敵なものを共存させて、価値を見出していく、伝えていく。D&DEPARTMENTはそんなことができる会社なのだろうな、と思うと同時に、わたしもそんな仕事をしていきたい!と気付くなどしました。